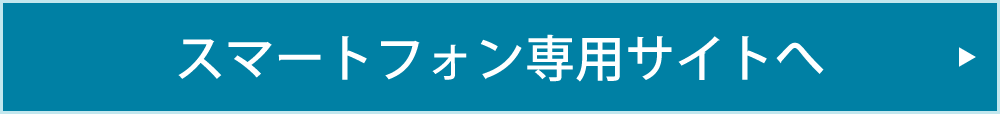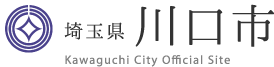自転車安全利用条例を制定しました
更新日:2025年08月01日
これまで、川口市においては、平成24年4月1日に施行された「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」に基づいた施策を実施し、自転車の安全な利用の促進を図ってまいりました。
しかしながら、本市における自転車が関係する事故の割合は、人身事故全体の約30%という高い割合を占めています。
そこで、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、かつ、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、「川口市自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制定し、今後は市民総ぐるみで自転車の安全な利用の促進に取り組みます。
施行日
平成30年4月1日(令和5年6月29日一部改正)
条例本文
川口市自転車の安全な利用の促進に関する条例 (PDFファイル: 145.9KB)
条例の概要
自転車の安全な利用の促進に関し、市、市民、自転車利用者、事業者及び関係団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項について定めています。
|
対象 |
責務 |
|---|---|
|
市 |
・自転車安全利用施策の総合的な推進(4条) |
|
市民 |
・家庭、職場、学校、地域社会等での自転車安全利用に関する自主的・積極的な取組の実施(5条) |
|
利用者 |
・運転者としての責任の自覚、道路交通法等の法令の遵守(6条1項) ・防犯対策(盗難防止のための施錠、ひったくり防止カバーの装着など)(6条2項) |
|
事業者 |
・自転車安全利用の自主的・積極的な取組の実施(7条1項) ・従業員に対する啓発(7条2項) |
|
関係団体 |
・市民の理解と協力が得られるよう自転車安全利用に関する自主的・積極的な取組の実施(8条) |
|
主体 |
内容 |
|---|---|
|
市 |
・市民、自転車利用者に対する交通安全教育の実施(10条1項) ・児童の発達の段階に応じた自転車交通安全教育の実施(10条2項) ・高齢者の特性に応じた自転車交通安全教育の実施(10条3項) |
|
保育所・ 学校長等 |
・生徒等の発達の段階に応じた自転車交通安全教育の実施(11条) ・保護者に対し、自転車の安全な利用に関する理解を深めるための啓発を実施(11条2項) |
|
保護者 |
・児童に対する自転車交通安全教育の実施(12条) |
|
項目 |
内容 |
|---|---|
|
小売業者による情報提供 |
・自転車の安全な利用に関する必要な情報の提供及び助言(9条) |
|
点検整備 |
・「利用者等」は、安全性の確保に必要な点検整備を実施(13条1項) ・「保護者」は、児童が自転車を利用するときは、安全性の確保に必要な点検整備を実施(13条2項) |
|
反射器材 |
・「利用者等」は、自転車の側面に反射器材を備付け(14条1項) ・「利用者」は、反射材の身体や衣服への装着(14条2項) ・「利用者」は、夜間のほか、夕方には前照灯を点灯(14条3項) |
|
広報及び 啓発等 |
・自転車の安全な利用の促進のために必要な広報・啓発活動の実施(15条1項) ・市民、自転車利用者へ、自転車が関係する交通事故の発生状況に関する情報の提供(15条2項) |
|
道路環境の整備 |
・歩行者、自転車、自動車が安全に通行できる道路環境の整備(16条) |
よくある質問
Q2.市民の責務とは何ですか?何をしなければならないのですか?
Q3.自転車利用者の責務とは何ですか?何をしなければならないのですか?
Q4.事業者の責務とは何ですか?何をしなければならないのですか?
Q5.関係団体の責務とは何ですか?何をしなければならないのですか?
Q6.自転車小売業者や自転車貸付け業者はどのような情報を提供すればよいのですか?
Q11.なぜ乗車用ヘルメットを着用しなければならないのですか?
Q14.埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例との違いは何ですか?
A1.市の責務とは何ですか?
市は、市民や関係団体などと連携し、協働しながら、自転車の安全な利用に関する施策(交通安全教育や広報啓発活動など)を総合的に推進します。
A2.市民の責務とは何ですか?何をしなければならないのですか?
市民は、自転車の安全な利用について理解を深め、家庭や学校、地域などにおいて話をするなど、自主的な取り組みを行うよう努めましょう。
取り組みの例として、「家庭において、自転車安全利用五則などの交通ルールについて確認をすること」や「自治会等で自転車の安全利用に関しての呼びかけをすること」などが挙げられます。
A3.自転車利用者の責務とは何ですか?何をしなければならないのですか?
自転車を利用する人は、交通ルールを守り、乳幼児や障害者、高齢者などを含めた歩行者や自動車、原動機付自転車などの通行を妨げないよう、安全に配慮した運転をしましょう。
また、自転車盗難防止のための施錠やひったくり防止のためのカバー装着などの防犯対策を行うとともに、防犯登録を受ける義務を必ず守りましょう。
A4.事業者の責務とは何ですか?何をしなければならないのですか?
従業員に対し、自転車の安全な利用に関する理解を深めさせ、自転車を利用するときの安全運転への意識向上に繋がるような啓発や取り組みを積極的に行うよう努めましょう。
取り組みの例として、「交通安全講習の開催」や「朝礼等での呼びかけ」などが挙げられます。
A5.関係団体の責務とは何ですか?何をしなければならないのですか?
交通安全に関する活動を行う関係団体は、市民から自転車の安全な利用について理解や協力が得られるよう、広報・啓発活動など積極的な取り組みを行うよう努めましょう。
A6.自転車小売業者や自転車貸付け業者はどのような情報を提供すればよいのですか?
自転車を購入しようとする人などには、自転車の安全利用に必要な情報の提供や助言を行うよう努めましょう。
必要な情報として「自転車安全利用五則などの交通ルール」、「反射材やヘルメット着用の重要性」や「自転車損害保険加入の必要性」などが挙げられます。
A7.市はどのような交通安全教育を行うのですか?
市は、警察などと連携し、市民に対し自転車交通安全教育を行います。
児童に対しては、学校長と連携して、その発達の段階に応じた交通安全教育を行います。
高齢者に対しては、その特性に応じた交通安全教育を行います。
また、社会情勢などの変化に対応した教育を行うため、必要に応じて『交通安全教育指針(国家公安委員会)』、『「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育(文部科学省)』などを参考とし教育内容の見直しを行います。
なお、市は市内の団体に対し、無料で交通安全教室を行っています。
事前予約制となりますので、あらかじめ担当課へお問い合わせください。
A8.保護者は児童に対して、何をすれば良いのですか?
保護者は、児童に対して、「自転車安全利用五則などの交通ルール」をはじめとする自転車の安全な利用についての教育を行うとともに、「児童の体格にあった自転車の選定」を行いましょう。
また、児童が自転車を利用するときにも「ヘルメットを着用させる」、「点検整備の実施」など必要な措置をとるよう努めましょう。
A9.なぜ反射材の着用が必要なのですか?
車から、歩行者や自転車が見えにくい夕方から夜間の時間帯は、反射材を着用することで、他者に自分の存在を知らせることができ、事故防止につながるためです。
A10.なぜ夕方にもライトをつけなければならないのですか?
夕方や夜間の走行では、昼間と比べて網膜に映る像がぼやけてしまうなど、視覚機能が低下します。
特に、秋や冬は日没までの時間が短く、夕方においても事故が多発する傾向にあります。
ライトを点灯することで歩行者や自転車が発見しやすくなり、また、他者に自分の存在を知らせることができ、事故防止に有つながるためです。
夜間だけでなく夕方もライトを点灯するよう努めましょう。
A11.なぜ乗車用ヘルメットを着用しなければならないのですか?
自転車乗用中の交通死亡事故の死因の多くが頭部損傷です。頭部を守るためにヘルメットを着用しましょう。
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日交付、令和5年4月1日施行)により、すべての自転車利用者に自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務になっています。
A12.道路環境の整備とは具体的に何をするのですか?
歩行者や自転車、自動車などが安全に通行できるよう、継続して交通安全施設(自転車レーン、路面表示、ガードレール、カーブミラーなど)の整備に取り組みます。
A13.自転車損害保険に加入しなければならないのですか?
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」において、自転車乗用中に起こした加害事故によって生じた、他者の生命や身体の損害を補償することが出来る保険などへの加入が義務付けられました。
個人の日常生活において生じた自転車事故に対応する個人賠償責任保険などへの加入のほか、事業者は、業務上の賠償事故を補償する保険などへの加入が必要になります。(詳しくは、自転車も保険に加入しましょう)
A14.埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例との違いは何ですか?
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」で定められていない市の責務を定めるほか、「幼児に対する自転車の交通安全教育」や「学校長などによる保護者への啓発」、「夕方の前照灯の点灯」について定めています。
また、市が実施する自転車の安全な利用に関する施策(交通安全教育や広報・啓発活動など)について、より具体的に定めることで、更なる自転車の安全利用の促進を図ります。