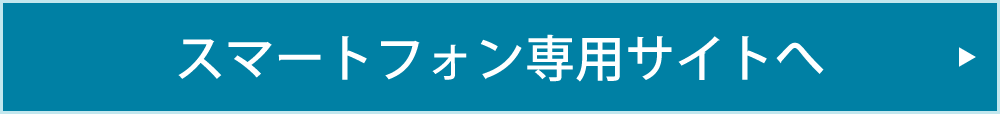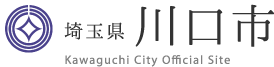生活支援体制整備事業とは
更新日:2024年10月01日
地域包括ケアシステムとは
団塊の世代が75歳以上となる2025年以降、少子化を背景として生産人口は減少し、医療・介護の専門職の担い手の確保は困難となる一方で、介護ニーズの高い85歳以上人口は2035年まで一貫して増加することが見込まれています。
高齢者が重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していくため、川口市では「高齢者が健やかに暮らし、活躍できるまちづくり・地域包括ケアシステムの発展」を目指し、取組を推進しています。

生活支援体制整備事業とは
高齢者の尊厳と自立した日常生活を地域で支えていくためには、総合事業として実施するサービス・活動事業及び一般介護予防事業並びに地域住民を含めた多様な主体による高齢者の自立した生活や介護予防に資する総合事業に該当しない多様な活動又は事業(以下、「生活支援・介護予防サービス」という)について、事業間での連動を図りながら実施することが重要です。
このため生活支援体制整備事業では、元気な高齢者をはじめとする多世代の地域住民が担い手として参加する住民主体の活動団体、社会福祉法人、民間企業、老人クラブ、民生委員等の多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築し、地域の支え合いの体制づくりを推進していくことを目的としています。
※上記地域包括ケアシステムの図における、「生活支援・介護予防」の支援が生活支援体制整備事業の該当箇所になります。
生活支援コーディネーターとは
生活支援コーディネーターとは、資源開発・ネットワーク構築・ニーズと取組みのマッチングを目的に、以下の業務を実施する”地域の調整役”です。
- 高齢者の支援ニーズ・関心事や地域住民を含む多様な主体の活動の状況の情報収集及び可視化
- 1を踏まえた、地域住民や多様な主体による生活支援・介護予防サービスの企画・立案、実施方法の検討に係る支援(活動の担い手又は支援者たり得る多様な主体との調整を含む)
- 地域住民・多様な主体・市の役割(地域住民が主体的に行う内容を含む。)の整理、実施目的の共有のための支援
- 生活支援・介護予防サービスの担い手(ボランティア等を含む。)の養成、組織化、具体的な活動とのマッチング
- 支援ニーズと生活支援・介護予防サービスとのマッチング
川口市では、生活支援コーディネーターを第1層(市圏域)に1名、第2層(日常生活圏域)に20名配置し、第1層生活支援コーディネーターはかわぐちボランティアセンターに、第2層生活支援コーディネーターは各地域包括支援センターに委託して実施しています。
協議体とは
協議体とは、生活支援コーディネーターが行うコーディネート業務を支援し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進することを目的にとした会議体で、以下の役割を担います。
- 生活支援コーディネーターの組織的な補完
- 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の可視化の推進(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)
- 企画、立案、方針策定を行う場(生活支援・介護予防サービスの担い手養成に係る企画等を含む。)
- 地域づくりにおける意識の統一を図る場
- 情報交換の場、働きかけの場等
- お問い合わせ
-
長寿支援課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7651(生きがい対策係直通)
電話:048-259-7652(支援係直通)
電話:048-271-9745(地域ケア係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7668
メールでのお問い合わせはこちら