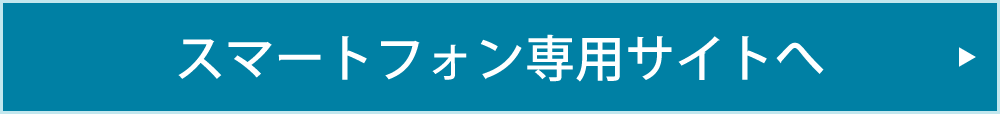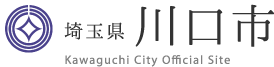ごみ収集車やごみ処理施設で火災が発生しています
更新日:2025年01月27日
市民の皆様に出来ることのお願いです!
正しいごみの分別により火災を防ぐことができます。
誤ったごみの分別により、ごみ収集車やごみ処理関連施設から出火する火災が発生しています。
不用品を処分する際は、指定するごみの分別ルールを確認しましょう。
火災発生事例
事例として、ごみ収集車で収集した一般ごみの袋から煙・炎が発生。
消火活動後、一般ごみの袋内に捨ててはいけないリチウムイオン充電池等が廃棄されている事象が散見されます。
近年、ごみ収集車やごみ処理施設にて出火した事例が散見され、特にリチウムイオン電池を含む製品及びエアゾール缶等が発火源となる火災です。
事例1
ごみ収集車が一般ごみを収集時に、モバイルバッテリーがごみ収集車内で圧縮等の外的要因により短絡し出火。

事例2
ごみ収集車が一般ごみを収集時、スプレー缶がごみ収集車内で圧縮され、スプレー缶に残っていた可燃性ガスに引火し出火。
火災を防止するためには…
- 不用品を処分する際は、地域のごみ回収方法をよく確認してその方法に従って処分しましょう。
- リチウムイオン電池内蔵製品を処分する際は、製品の取扱説明書をよく確認しましょう。
- スプレー缶やライターをやむを得ず使い切らずに捨てる時には、火気のない通気性の良い屋外で残存ガスがなくなるまで噴射してから廃棄しましょう。
住宅における電気火災に係る防火安全対策検討会報告書(概要版)より抜粋

第4章 廃棄物処理施設等で発生した充電式電池等を原因とする火災の統計の分析と事例調査の結果
1 廃棄物処理施設等で発生した充電式電池等を原因とする火災の統計の分析
(1)調査概要
第1回検討会において、「リチウムイオン蓄電池を含む充電式電池については、廃棄物処理施設及び塵芥車における火災の状況等も調査し、必要に応じて注意喚起すべきではないか」との意見を踏まえ、追加の分析・調査を行った。
ア 分析対象
過去10年間(平成24年から令和3年まで)の火災統計のうち、以下の条件に当てはまるもの
(ア)「廃棄物処理施設」において発生した火災で、充電式電池、リチウム電池※(以下、「充電式電池等」という。)が発火源であるもの
(イ)「塵芥車」において発生した火災で、充電式電池等が発火源であるもの
※リチウム電池は一次電池であるが、二次電池であるリチウムイオン電池が含まれる可能性があるため調査対象に含めている。
イ 留意事項
本分析における火災件数は、「廃棄物処理業」を業態とする施設・車両における火災のうち、防火対象物用途区分が「廃棄物処理施設」及び「塵芥車」に該当する可能性があるものを集計している。
(2) 廃棄物処理施設における火災の件数
廃棄物処理施設における過去10年間の火災件数の推移について分析した(図4-1)。

廃棄物処理施設における火災は、令和3年は減少しているものの、平成28年以降、増加傾向が見られる。廃棄物処理施設に発生した火災のうち、充電式電池等についてみると、平成30年以降に増加していることが分かる。
(3) 塵芥車における火災の件数
塵芥車における過去10年間の火災件数の推移について分析した。(図4-2)

塵芥車における火災についても、令和3年は減少が見られる。過去10年間において、平成24年から平成30年までは年250件程度で推移していたが、令和元年から増加傾向が見られる。
また、充電式電池等を発火源とする火災についても、平成25年から徐々に増加し、令和2年、3年には年間50件程度発生している。
2 廃棄物処理施設等で発生した充電式電池等を原因とする火災事例の調査
(1) 調査概要
本調査は、「1 廃棄物処理施設等で発生した充電式電池等を原因とする火災の統計の分析」を踏まえ、本検討会に参加している4消防本部を対象に、廃棄物処理施設・塵芥車における充電式電池等を原因とする火災の事例調査を実施したもの。
ア 調査対象
廃棄物処理施設・塵芥車において、充電式電池等を原因として発生した火災
イ 調査内容
具体的な出火に至る背景(不適当な廃棄等)や発火源となった充電式電池製品の調査。
ウ 対象件数(経過が不明を除く。)
調査対象2項目のうち、各項目直近の20件ずつ。又は、直近3年分(令和2年から令和4年まで)
エ 調査地域
本検討部会に参加している4消防本部の管轄区域(札幌市消防局、東京消防庁、大阪市消防局、神戸市消防局)
オ 留意事項
・ 本調査結果は、調査地域を限定して火災事例を収集・分析したものであり、全国の火災の傾向とは必ずしも一致しない可能性がある。
・ 本調査の調査件数には上限があるため、必ずしも対象ごとの火災件数を表すものではない。
(2) 事例調査の結果
ア 廃棄物処理施設
参加消防本部の管轄区域で発生した廃棄物処理施設における火災事例数は全部で28件あり、全て分別されずに廃棄された充電式電池から出火した火災であった。
火災原因となった充電式電池を含む製品は、ほとんどが特定できなかったものの、特定できたものでは、モバイルバッテリー1件、コードレス掃除機1件であった。
廃棄物処理施設における火災では、主に、廃棄物処理施設の破砕機でリチウムイオン蓄電池が破砕された際に、電池のセルが破損し短絡することで火花が発生し、周囲の可燃物(ごみ)に着火し出火するケースが多く見られた。
イ 塵芥車
参加消防本部の管轄区域で発生した塵芥車における火災事例数は全部で 47 件であり、廃棄物処理施設と同じく、全て分別がなされず廃棄された充電式電池等から出火した火災であった。
火災原因となった充電式電池を含む製品は、モバイルバッテリー等(電子たばこなどを含む。)10 件、コードレス掃除機5件、ノートパソコン2件、電動アシスト自転車2件、電動キックボード1件、ポータブル DVD プレーヤー1件、であり、製品が特定できなかった事例が 26 件であった。
塵芥車における火災は、回収したごみの中に、本来回収対象ではない充電式電池が他のゴミと一緒に廃棄され、塵芥車の回転板により充電式電池に外力が加わった際に、電池のセルが破損し短絡することで火花が発生し、周囲の可燃物(ごみ)に着火し出火に至るケースが多い.
(3)まとめ
廃棄物処理施設・塵芥車で発生した火災件数は増加しており、また、充電式電池等を発火源とする火災についても増加し、廃棄物処理施設等で発生する火災の一定割合を占めているところである。
近年、廃棄物処理施設等で充電式電池等を原因とした火災が発生し、通常の廃棄物処理に支障をきたす事例が全国で発生しているが、今回の調査から、分別されずに処分されたことで火災に至っていることが確認された。
こうした「不適当な廃棄」への対策としては、充電式電池等の処分方法が分からず不燃ごみ等と一緒に廃棄されていることが考えられるため、充電式電池を分別せずに廃棄した場合に、火災の原因となる危険性があることを注意喚起するとともに、充電式電池の正しい廃棄方法を周知する必要があると考えられる。
第5章 まとめ
2 廃棄物処理施設等で発生した充電式電池等を原因とする火災対策
近年、廃棄物処理施設等で充電式電池等を原因とした火災が発生し、通常の廃棄物処理に支障をきたす事例が全国で発生しているが、今回の調査から、分別されずに処分されたことで火災に至っていることが確認された。
同様の火災を防ぐためには、充電式電池を分別せずに廃棄した場合に、火災の原因となる危険性があることを注意喚起するとともに、充電式電池の正しい廃棄方法を周知する必要がある。
今回の検討から得られた事例を基に、今後は、それぞれの要因に応じた具体的な火災予防の方法について注意喚起を行うことが求められる。
※「住宅における電気火災に係る防火安全対策検討会報告書(概要版) 令和6年3月」(消防庁 https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-141/03/houkokusyo1.pdf)を加工して作成
リチウムイオン電池混入防止 啓発ポスター・チラシ
出典元:(公財)日本容器包装リサイクル協会
- お問い合わせ
-
予防課
所在地:〒333-0848川口市芝下2-1-1(消防局3階)
電話:048-261-8371(予防課代表)
048-261-8371(予防係)
048-261-8373(危険物係)
048-261-8379(火災調査係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-262-4850