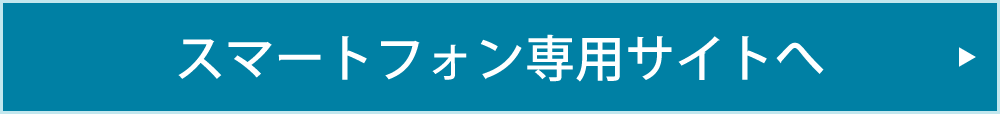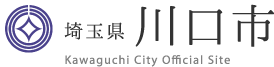高額療養費制度について
更新日:2025年08月21日
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
上限額を超えたお支払いを行った世帯には、最短で診療月の3カ月後の下旬に、国民健康保険課より世帯主あてに高額療養費支給申請書を送付します。
申請書が届きましたら申請してください。
また、医療費の支払い額が高額になるとき、マイナ保険証や限度額適用認定証等の提示で支払額を自己負担限度額までに抑えることができます。
詳細については「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について」のページをご覧ください。
70歳未満のかたの場合
|
適用区分 |
自己負担限度額 (注釈)3回目まで |
自己負担限度額 (注釈)4回目以降 |
|---|---|---|
| ア(所得901万円超) | 252,600円+(総医療費−842,000円)の1% | 140,100円 |
| イ(所得600万円超 901万円以下) | 167,400円+(総医療費−558,000円)の1% | 93,000円 |
| ウ(所得210万円超 600万円以下) | 80,100円+(総医療費−267,000円)の1% | 44,400円 |
| エ(所得210万円以下) | 57,600円 | 44,400円 |
| オ(住民税非課税世帯) | 35,400円 | 24,600円 |
所得は、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額です。
適用区分は、月の初日における世帯状況により判定します。
月の途中に加入者の異動があった場合は、新たな区分は翌月初日(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日)から適用します。
過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給を4回以上受けた場合、「4回目以降の限度額」が適用されます。
自己負担額の計算方法(70歳未満のかた)
暦月ごとに計算(月の1日から末日)
2つ以上の医療機関等にかかった場合は別計算
ただし、それぞれの自己負担額が21,000円以上の場合は合算
同じ医療機関でも、医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算
ただし、それぞれの自己負担額が21,000円以上の場合は合算
入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の医療行為は対象外
70歳から74歳のかたの場合
70歳から74歳の現役並み所得者3及び一般の世帯のかたは、マイナ保険証、資格確認書のいずれかを提示することで自己負担限度額までの支払いとなりますので、限度額適用認定証を申請する必要はありません。
70歳以上のかたの適用区分と自己負担限度額(月額)
|
適用区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) (注釈)4回目以降 |
認定証 の申請 |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)の1% | 140,100円 | 不要 | |
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(総医療費-558,000円)の1% | 93,000円 | 可能 | |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+(総医療費-267,000円)の1% | 44,400円 | 可能 | |
| 一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 |
44,400円 |
不要 |
| 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | 可能 | |
| 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 | 可能 | |
課税所得は、住民税課税所得です。
適用区分は、月の初日における世帯状況により判定します。
月の途中に加入者の異動があった場合は、新たな区分は翌月初日(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日)から適用します。
過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給を4回以上受けた場合、「4回目以降の限度額」が適用されます。
70歳以上の外来療養に係る年間の限度額
基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得に該当する場合について、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)のうち一般または低所得であった月の外来療養に係る自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合は、その超える分を支給します。
自己負担額の計算方法(70歳から74歳のかた)
暦月ごとに計算(月の1日から末日)
外来は個人単位でまとめ(現役並み所得者は除く)、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
病院・診療所、歯科の区別なく合算
入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の医療行為は対象外
70歳未満と、70歳から74歳のかたが同一世帯の場合
70歳以上74歳以下のかたの自己負担額を計算。
次に70歳未満のかたの合算対象基準額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満のかたの自己負担限度額を当てはめて計算。
多数回該当の引き継ぎについて
平成30年4月以降は埼玉県が国民健康保険の保険者となることに伴い、県内の他市町村へ住所異動した場合、世帯としての継続性が認められれば、県内での住所異動は資格喪失とならないため、高額療養費の該当回数を引き継ぐことになります。
高額療養費受領委任払い制度
高額の医療費(一部負担金)を支払うことが困難な場合、「高額療養費」の受領を世帯主が医療機関に委任することにより、医療機関への支払いが自己負担限度額までで済む「高額療養費受領委任払い制度」があります。
次の適用条件に該当し利用を希望される方(世帯主)は、国民健康保険課にご相談ください。
適用条件
1.自己資金だけでは、療養に関わる医療費(一部負担金)の支払いが困難であること。
2.高額療養費の受領権限の委任について、医療機関の同意が得られること。
3.保険税を納付していること。
4.療養の原因が、交通事故などの第三者行為や給付の制限がかかるものでないこと。
5.同一世帯内の国保加入者全員(他の医療保険に加入する国保税納税義務者を含む)の所得の状況が確認できること。
- お問い合わせ
-
国民健康保険課 給付係(第二本庁舎2階1番窓口)
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎2階)
電話:048-259-7670(給付係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4950
メールでのお問い合わせはこちら