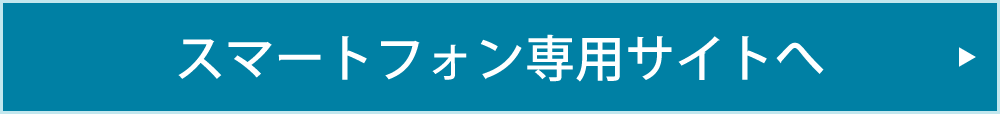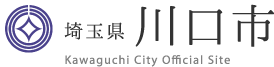被災建築物応急危険度判定活動について
更新日:2020年07月22日
被災建築物応急危険度判定活動とは?
地震後の余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を未然に防止するため、被災した建築物の被害の状況を調査し、その建築物が使用できるか否かの判定・表示を応急的に行うことです。
調査結果は「調査済」(緑紙)、「要注意」(黄紙)、「危険」(赤紙)の三種類の判定ステッカー(色紙)のいずれかにより、見やすい場所に表示します。
罹災証明のための被害調査ではなく、建築物が使用できるか否かを応急的に判定するものです。

被災建築物応急危険度判定士とは?
被災建築物応急危険度判定士は、被災地において、市長(被災建築物応急危険度判定実施本部)の要請により、被災建築物の応急危険度判定をボランティアで行う建築技術者です。被災建築物応急危険度判定士は、「埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱」に基づき、知事が行う講習会等を受講して認定登録を受けています。被災建築物応急危険度判定士は、判定活動に従事する場合、常に身分を証明する登録証を携帯し、「応急危険度判定士」と明示した腕章及びヘルメットを着用します。

被災建築物応急危険度判定と罹災証明のための被害調査の違いは?
被災建築物応急危険度判定は、地震後の余震等による二次災害を未然に防止するため、応急的に建物の安全性をチェックするものであり、被害調査は、建築物の資産価値的な面(損傷の程度)を調査するので、被災建築物応急危険度判定とは、視点・内容が異なります。
例えば、建物本体の損傷が軽微な場合(資産価値的な損傷が少ない場合)でも、地震後の余震等により看板やクーラーの室外機等が落下する危険性が高い場合には、建物使用者や歩行者等に及ぼす危険の度合いを判定するという観点から、「危険」(赤紙)と判定されることがあります。
建築士の皆様へ
建築士の資格はあるが、まだ被災建築物応急危険度判定士の登録をしていない人は、被災建築物応急危険度判定活動に参加することはできません。是非、被災建築物応急危険度判定士への認定登録をするようお願いいたします。
認定登録や講習会等については、社団法人埼玉建築士会のホームページをご覧下さい。
ご存知ですか?「応急危険度判定士」 (PDFファイル: 360.7KB)
関連先リンク
- お問い合わせ
-
建築安全課建築指導係
所在地:川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
直通:048-242-6344(直通)
窓口受付時間:9時00分~16時30分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-4805
メールでのお問い合わせはこちら