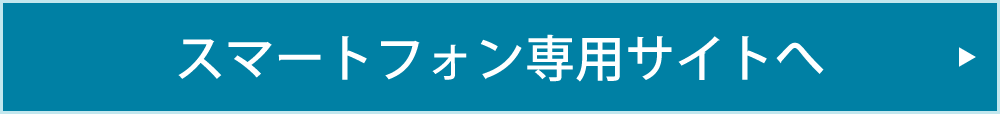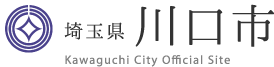保育所等において使用する様式
更新日:2021年04月01日
保育所等における保育については、保育所保育指針に基づき行うこととなります。各施設におかれましては、内容を理解していただきますようお願いいたします。
また、保育所等において使用する様式を以下のとおり掲載いたします。あくまで参考様式となりますが、必要に応じて御活用ください。
保育計画
保育所保育指針において、各保育所は、 保育の全体像を包括的に示すものとして全体的な計画を作成し、これに基づく指導計画等を通じて保育を行うこととされています。このことから、以下の保育計画を作成することが求められています。
全体的な計画
保育所等は、保育の目標を達成するために、保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえて、保育の内容が組織的・計画的に構成され、保育所等の生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、全体的な計画を作成しなければなりません。
また、全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しをもって作成してください。
指導計画
全体的な計画に基づき、次の指導計画を作成しなければなりません。
・長期的な指導計画(年間、月案等)
・短期的な指導計画(週案、日案等)
・児童ごとの個別の指導計画(障害児、3歳未満児に限る)
・デイリープログラム
指導計画は全体的な計画に基づいて保育を実施する際のより具体的な方向性を示すものであり、実際の子どもの姿に基づいて、ある時期における保育のねらいと内容・環境・そこで予想される子どもの活動や、それに応じた保育士等の援助・配慮すべき事項・家庭との連携等を考え、作成するものです。
年間指導計画(1~5歳児)(Excelファイル:39.5KB)
月別指導計画(1~5歳児)(Excelファイル:48.5KB)
保育日誌
保育日誌は、日々の保育がどのように行われているか、記録するためのものです。
日誌に記載する内容は「天候」、「出席人数」、「カリキュラムの内容」等です。
保育を行うなかで、実践、反省、振り返り、評価につながるように作成することが望まれます。
作成する際は、1日の保育の活動内容のポイントを押さえて可能な限り具体的に書くことが必要です。今後の振り返りや評価に生かせるように作成するものです。
保育内容等の自己評価
保育内容等の評価は 、子ども の豊かで健やかな育ちに資する保育の質の確保・向上 を目 的として行われます。保育内容等の評価は、 「保育士等が自らの保育を振り返って行う自己評価 」と、 それを踏まえ、 「保育所が組織全体で共通理解をもって 取り組む自己評価 」が基本となります。
職員の自己評価
保育所保育指針において、職員は、保育の記録を通して、計画とそれに基づく実践を振り返り、自己評価を行うことが求められています。
保育所の自己評価
保育所保育指針において、保育所等は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や職員の自己評価を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
連絡帳
保育所保育指針において、日常の保育に関連した様々な機会を活用し、子どもの日々の様子の伝達や収集、保育所保育の意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努めることと定められており、その機会の1つとして、連絡帳の活用があります。
特に3歳児未満の子どもは、言葉でのやり取りが難しいため、連絡帳を活用してください。
事故防止及び事故発生時の対応
保育施設における子どもの死亡事故などの重大事故は、全国的に見ると毎年発生しています。
日々の教育・保育においては、乳幼児の主体的な活動を尊重し、支援する必要があり、子どもが成長していく過程で怪我が一切発生しないことは現実的には考えにくいものです。
そうした中で、施設・事業所における事故、特に、死亡や重篤な事故とならないよう予防と事故後の適切な対応を行うことが重要です。
事故防止及び事故発生時の対応については、国の作成した「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」を参考にしてください。
〈こども家庭庁ホームページ〉https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline/
事故発生時の報告
保育所等において、重大事故が発生した場合は、市への報告が必要となります。
万が一、重大事故が発生した際は、速やかに市へ御連絡ください。重大事故の定義については、下記の通知を御覧ください。
ヒヤリハット
重大事故の発生防止、予防については、ヒヤリハット報告の収集及び分析が有効です。
重大事故が発生するリスクがあった場面に関わった場合には、ヒヤリハット報告を作成しましょう。
集められたヒヤリハット報告の中から、事故が発生しやすい場面において、リスクに対しての要因分析を行い、事故防止対策を講じてください。
ヒヤリハット・アクシデント記録(Wordファイル:17.9KB)
ブレスチェック
睡眠中は保育事故が発生しやすい場面です。ブレスチェックにより、定期的に子どもの呼吸・体位、睡眠状態を点検してください。
ブレスチェックを実施した際は、必ず記録をしてください。
ブレスチェックは以下の間隔で実施してください。
0歳児 : 5分に1回以上
1歳児 : 10分に1回以上
2歳児 : 15分に1回以上
※3歳児以上については、常に目を離さず、60分毎に午睡時安全確認表への記録をお願いします
ブレスチェック表(0~1歳児)(Excelファイル:1.6MB)
感染症対策
保育所等における感染症対策では、抵抗力が弱く、身体の機能が未熟であるという乳幼児の特性等を踏まえ、感染症に対する正しい知識や情報に基づき、適切に対応することが求められます。
また、日々感染予防の努力を続けていても、保育所等内への様々な感染症の侵入・流行を完全に阻止することは不可能です。このことを理解した上で、感染症が発生した場合の流行規模を最小限にすることを目標として対策を行うことが重要です。
日頃の感染症対策は、国の作成した「保育所における感染症対策ガイドライン」を参考に実施してください。
登所届
保育所等では、乳幼児が長時間にわたり集団で生活する環境であることを踏まえ、周囲への感染拡大を防止することが求められます。
このことから、学校保健安全法施行規則に規定する出席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ登所のめやすを確認しておく必要があります。
また、子どもの病気治癒後の登所については、登所届の提出を求めてください。
【今シーズンのインフルエンザの対応について】
厚生労働省から、インフルエンザの陰性を証明することが一般的に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから、インフルエンザの罹患(りかん)後に、治癒証明や陰性証明を求めることは望ましくないとの見解が示されました。
このことから、川口市では、今シーズンのインフルエンザ罹患後の対応について、登所届の代わりに、保護者が記入する経過報告書等(治癒後の受診が不要)による対応も可能といたします。
※各保育所等において感染対策の観点から、登所届等の提出を求めることを妨げるものではありません
与薬依頼書
保育所等で行う与薬については、医師が処方したものに限ります。
与薬を行う際は、与薬依頼書を保護者に記入してもらい、以下に留意した適切な管理、与薬を行わなければなりません。
副作用の危険があるため、すでに家庭で与薬を行っている薬のみとしてください。(保育所等での与薬が初めてとならないようにしてください)
健康診断・発育チェック
保育所等は年に2回の定期健康を学校保健安全法施行規則の規定に準じて実施しなければなりません。
また、子どもの発育状態把握のため、定期的に身長や体重等を計測することが必要です。
その他の様式
- お問い合わせ
-
保育運営課指導係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎3階)
電話:048-258-4098(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-4959
メールでのお問い合わせはこちら